| トップページへ戻る |
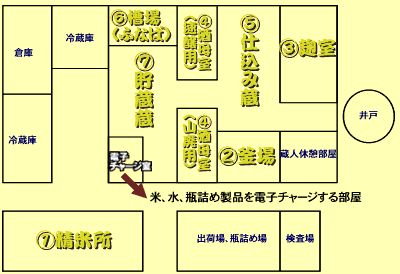
|
③麹室(こうじむろ)−「納豆ダメ、みかんも」 |
|
|
|
①放冷 当たり前ですが蒸しあがった米は熱い!それを40〜35℃ぐらいまでに冷やしている作業です。蒸し米を潰さないよう、手で蒸し米をほぐしながら、水分を飛ばして温度を下げます。目的の温度になったら室(むろ:麹室)に引き込みます。〜写真下に進む。 |
|
|
②引き込み〜寝かせ(あら熱とり) 引き込まれた蒸し米は、室の中でゆっくりと表面を乾かします。こうすることで、蒸し米の表面が乾き、その内側が柔らかい「外硬内軟」の蒸し米になります。麹菌も生き物ですので、蒸し米の表面が柔らかい時は楽して表面に生えようとします。このような麹は充分な糖化力を持ちません。これとは逆に「外硬内軟」蒸し米の場合、米の内側に食い込もう(破精込もう)とするので、この時もろみで必要な糖化力が備わる訳です。 |
|
|
左は35%(大吟醸用)、右は45%精白(山廃純米大吟醸用)の山田錦の蒸し米です。ちょっと分かりづらいですが、左の米のほうが白く見えるはずです。このように磨いてない米は「黒い米」、磨いてるものは「白い米」と言い、もろみやその泡の色まで違います。写真は、いずれも大吟醸の蒸し米ですが、10%精白度が違うだけでも色が変わってきます。 |

|
③種きり 34〜32℃にて、麹師がもやし(種麹)をふってるとこです。ここから約2日かけて麹になります。ここではごらんの通り嫌でも裸(ウチは!)で作業します。麹と裸の付き合い。なんちゃって!でも嘘じゃあないっすよ! |
|
|
④くるみ 適温にてもやしをふった後は、冷えないよう、乾燥しないように布や毛布で幾重に覆います。室に蒸し米を引き込んで、2時間後にはこのようにくるみます。夜の切り返し作業までこのままで、その作業が済んだら再び包んで翌朝まで待ちます。 |
|
|
⑤切り返し 朝にくるんだ蒸し米をくずして塊をほぐす作業を切り返しといいます。蒸し米の香が消える頃、または、うるみが出てくる頃が目安とされま。麹菌を植えつけてから12時間してからでしょうか、ウチでは12時間後にしています。塊となった蒸し米を一粒一粒ほぐすのは大変で労力が要ります。最近ではこの作業をわざと省略する蔵もありますが、ウチは水分、温度を均一にしたいので、毎晩酌後に、勢いでやっています。 |
|
|
⑥盛り〜仲仕事〜仕舞い仕事  二日目の朝。盛りという作業
(左上)です。これまで包んでいた蒸し米を一粒一粒、ばらばらっととなるよう揉んだ後、麹蓋(こうじぶた)という箱に「盛って」いきます。この時の蒸し米の表面には、米一粒あたり、2〜4個ほどの白く小さな点が出現し、初めて麹菌が目の前に現れた訳です。ここから、自らの発酵熱で温度が上がり、34〜36℃で仲仕事
(上左)。38〜41℃で仕舞い仕事(上右)をします。最高は42〜45℃に。この温度経過で仕込別に麹を造り分けていきます。仕舞い仕事以降、麹師は深夜にも何度か起き、温度のチェックをします。 二日目の朝。盛りという作業
(左上)です。これまで包んでいた蒸し米を一粒一粒、ばらばらっととなるよう揉んだ後、麹蓋(こうじぶた)という箱に「盛って」いきます。この時の蒸し米の表面には、米一粒あたり、2〜4個ほどの白く小さな点が出現し、初めて麹菌が目の前に現れた訳です。ここから、自らの発酵熱で温度が上がり、34〜36℃で仲仕事
(上左)。38〜41℃で仕舞い仕事(上右)をします。最高は42〜45℃に。この温度経過で仕込別に麹を造り分けていきます。仕舞い仕事以降、麹師は深夜にも何度か起き、温度のチェックをします。
|

|
 ⑦出麹 ⑦出麹出麹の絵。室に蒸し米を引き込んでから48〜54時間でようやく完成です。しばらく、室内で乾かした後、麹を枯らし場に入れ、翌朝の仕込みに用います。 |
このページに関するお問い合わせは
株式会社 鈴木酒造店
TEL:0240-35-2337 FAX:0240-35-3107